第四日目:6月12日( 水曜日 )
黄龍の入り口までほんの数秒100mの所、一番近いホテルである。
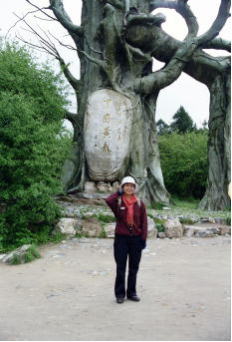
現地ガイドの王さんが、二組のカップルにパスポートを出すように促していた。それを持ってチケットを買いに行き、また戻ってきて3人からまたパスポートを受けとっていった。今年から65歳以上の人はパスポートが要るのだそうである。(昨年までは70歳以上でよかった)高齢者に保険を掛けるためパスポートを提示するのだそうである。
[黄龍]地区は徒歩によるトレッキング観光である。ゲートをくぐったら、それぞれのペースで園内を散策し、ホテルのロビーに午後1時に集合ということになった。
[黄龍入り口(3,100m)]⇒(500m・30分)⇒[迎賓彩池(3,216m)]⇒(200m・15分)⇒[飛瀑流輝(3,233m)]⇒(200m・15分)⇒[洗身洞瀑布・黄龍彩池(3,281m)]⇒(300m・20分)⇒[盆景池(3,335m)]⇒(400m・25分)⇒[明境倒映池(3,381m)]計算(300m・20分)⇒[争艶池(3,431m)]⇒(1,500m・50分)⇒[五彩池(3,552m)]⇒(200m・20分)⇒[転花池(3,570m)]⇒(3,600m・70分)⇒[黄龍出口]
尾本さんの御主人は高山病が回復せずホテルで休むことになった。返す返すも残念なことである。実際に自分の目で景観を確かめられないなんて、ここまで来ていながら気の毒だった。
妻は「具合が悪くなったら駕籠に乗る。せっかくここまで来てこの夢の世界を見られないなんてつまらない、頑張ってみるわ」と気を引き締めて出発した。

私は1998年10月にガイドを雇って一人で“黄龍・九寨溝”へ来ているから、今回は2度目である。あのときの感動が忘れられない。妻が元気に動き回れるうちに一度見せてあげたいというのが今回の目的である。
4,200mの峠も舗装されて、4年前には入り口の周りは何もなかったのに、この変わり様には目をひん剥かれる程驚いた。
この山奥に良くもまあこんな大きなホテルを幾つも拵えたものである。とてつもなく大きな駐車場も完備されていた。
4年前は、狭苦しいお寺の通用門でしかなかった入り口が、コンクリート造りのでっかい建物になっていた。侘びしい昔の入り口のままではいけなかったのだろうか?
入り口で出鼻をくじかれて、中も変な風にいじくられていなければいいな? と心配になってきた。
[黄龍寺]は四川省の松潘県、玉翠山の麓に建つ寺院で、明代の創建で、前・中・後の三寺で構成されたが、現在は後寺のみ残っている。
[五彩池]は旧前寺(入り口付近)と後寺との間にある池の総称で、1,000を超す大小さまざまな池が段々畑の様に点在する。水面が多彩に輝くことがその名の由来である。
ゲートをくぐると、駕籠屋の客引きが一斉に群がってくる。[駕籠と言っても日本の様なものではなく中国式・赤、青、緑、黄の原色に彩られた・屋根付き背もたれ椅子]の両肘掛けの下位置に、二本の竹が(4mぐらい)取り付けられており、竹の先のほうは角材で固定してある。
更にその先端には布で織った帯状の紐が結わえ付けてある。それを首と肩に乗せて、二人の駕籠かきが担ぐのである。今回のツアーには高齢者が多いので、5カップル位の人が乗った。
登りだけだとチップを含めて400元(6400円)。往復だと700元(11,900円)。個人で交渉すると安く乗れるが、途中でチップを吊り上げてくる(何処の国も雲助の常套手段)とかで、希望者はガイドにおまかせということにする。
担ぐ方は訓練を受けたベテラン駕籠かきだが、その駕籠に乗る方は初めての経験だ。半分仰向けにされたような格好で、かなり急な勾配を担ぎ上げられる。駕籠は上下にゆさゆさ揺れる。じっと乗っているだけだから身体が段々冷えてくる。見た目でも乗っているのは楽じゃない。小柄な女性を乗せた駕籠かきはラッキーだろうが、大男を担ぐ羽目になった駕籠かきは、さぞかしきついことだろうと思った。
そんな光景を見て、妻は頑張って歩くと決めたようだ。私は4年前には頂上まで行けなかったので、今回こそは何が何でも一番美しい “転花池”目指して写真撮影に挑む決意である。
歩き始めて、遊歩道が作り直され、完備されていることに気が付いた。4年前の歩道も木は敷いてあった。幅60cmぐらいの板に、垂木を横にした滑り止めが打ってあっただけの歩道が、幅2mも有ろうか、びっしり敷き詰めてある。
自然の木を守るためか遊歩道上に木の生えている所は丸く刳りぬいてある。観光客が増えたから、自然を守ろうという所なのだろうが、こいつが写真のじゃまになる。“黄龍”が余り有名になりすぎてしまって、がっかり気分である。私達が入園したのはゲートが開いて間もなくだった。未だ人はまばらだった。美しい段々池の写真を撮るのに、なるべく人は入れたくない。
そこでツアーの人達のことはさて置いて、写真を撮りながら先頭を歩いた。

朝の気温は10度くらい? 私はTシャツの上にセーターを着、更に薄手のジャンパー・ズボンはGパン姿でスタート。
私が見た4年前のあのとうとうと流れる水がない? 日本は雨期だから、こちらもさぞかし水が豊富なのだろうと当てずっぽうで6月の私の誕生日がらみを選んだが、アルプスの雪解け水はすでに涸れてしまって、乾期に入っていた。
雨期は7月に入ってからで、所どころ、段々池の水は干上がっている。石灰石が剥き出しになった池はいただけない。
それでさえ、初めてここを訪れた人ならば、水が少なくてもこの奇観に目を見張る。
登り3.8㎞の途中には、水が織りなす美しい旋律が私達を生き返らせてくれた。水の嵩こそ少ないけれど、エメラルドグリーンあり、紺碧あり、緑がかった色の水も垣間見られて浮き浮きする。
生憎の曇り空で、太陽光が山との反射で語り掛ける、水との対話を聞くことが出来ないのが残念だった。でもでもここは夢の別天地なのである。地球のウエットな横顔のそのまた一断片を覗いた気分で、生きていて良かったと思っちゃう瞬間なのである。
標高3,500mを超す丘陵地帯に、茘枝(れいし)の木が茂っている。 《夏の国の禹(う)王が治水のために訪れた時、黄龍が舟を背負ってきた》と言う伝説が残っている。
私達は左側の板敷きの遊歩道を歩いた。駕籠に乗った人達は右側の土を固めた歩道を登る。時々カメラ写りの良い所で一休み、駕籠かき人夫がシャッター押しのサービスもしてくれていた。
空気が薄いせいか、登りはキツかった。周りに青々とした草木が生い茂っているのだから、空気は豊富のはずなのに? すぐに呼吸困難になってしまった。
途中で知り合った呼和浩特(ふふほと・チンギスハーンの生地)の女性から、後ろ向きに登れば苦しくないと、高地登山の呼吸法を教わった。
歩けば暑くなってくる。ジャンパーを脱ぎ、セーターも脱いで、Tシャツで丁度いい。が、立ち止まって景色に見とれているとすぐに冷え込んでしまうから、セーターを脱いだり着たりで忙しかった。

ついに[黄龍寺]迄辿り着いた。寺院は大改修工事中で、瓦をふき直し、壁も全部新しい石を積み上げて交換していた。既に柱を真っ赤に塗り替えてあった。足場が組んであり、中に入ることは出来なかった。
お寺の2階の窓から撮ったら、お目当ての[転花池]が綺麗に写っただろうにと、今回も後悔が残った。


「随分早かったですね。元気ですね」黄龍寺で待っていた王さんからお褒めの言葉を戴き、見晴台の位置を聞き、其処まで最後の一踏ん張りである。
生憎空模様が悪くなり、雨がぽつぽつ降ってきた。いろんな顔の段々池を見ながら登ってきたが、見晴台から見下ろす段々池の群集は、“素敵”と思わず声が出た。晴れていたらもっと綺麗なのだろうなあ? 少し残念な気持ちになった。 ここに来たこの状態が “夢の世界”じゃないか。そう言い聞かせるより仕方がなかった。
先ほどの中国人女性も登ってきたので、一緒に記念撮影。住所を書いて貰い、必ず送りますからと約束した。すると急にサービスが良くなって、下で買ってきたという真っ赤な花柄の傘を取り出して、傘を差して五色の池を背景に写真を撮りなさいと進めてくれた。妻の御満悦な顔は、一流のモデルさん顔だった。
見晴台からちょっと横道を登ると、黄龍の源泉に辿り着ける。側の木に教典を印刷した真っ赤な布が吊してあり、その脇ににはこれまた真っ赤な“罌粟(けし)”の花が数輪咲いていた。透明な水が地層からわき出している。この源泉を見られたのは何回も来ている添乗員の徳山さんが昨年やはり添乗で来た時に発見したからで、ここまで登ってくる人は殆ど居ないそうである。

雨交じりの黄龍・五彩池・転花池付近を堪能し、カッパを着て下山した。 見晴台から左の方に小高い林道が伸びている。
その林道から見下ろした[転花池]全景が又素晴らしい景観だった。目を細めると、海の入り江に中くらいの波が押し寄せている様にも見える。
尾根の陰が水の色加減を変えるのだが、こぼれ込む光の反射が強くって、写真を撮る際の絞りの調整に苦労した。
ゆっくり景観を楽しみながら降りて来ると、沢山の中国人旅行者が登ってきた。
ホテルの部屋にあったゴム製の酸素ボンベを脇に抱えて、酸素を吸いながら登ってくるのである。南米とかスイスにも行ったが、こんなおかしなボンベは初めてだし、なんか邪魔くさいお荷物に思えた。
予定より1時間近く早くホテルに着いた。もう高山病の心配はなさそうだ。ホテルのロビーで飲んだ缶ビールは美味かった。
宇宙の中の地球という小さな星が、何億年もの地殻変動を繰り返し、おわしますのか神が創造なされたのではないかというような、摩訶不思議な奇観をここに造り上げたのだ。
岷山山脈の主峰、雪宝山の麓の標高3,500mに鬱蒼とした樹海を育み、包み込むようにエメラルドグリーンの湖沼群を生んだ。
地表に露出した石灰岩層にできた窪みが、段々状に連なり、水のマジックとも表現できそう、深さや光の加減で微妙に濃淡を演出してくれている。
乾期で水が少ないのが残念だったが、初めてここを訪れた人の目には、まさに“神秘的な別世界”“童話の園”だった。
[松潘]の郵便局で買った切手を貼って、取り敢えず10枚の[絵はがき]を黄龍の崋龍山荘(ホテル)のフロントに持っていった。日本への国際郵便料(はがき)は、4元2角( 67円20銭)だが、4元8角(76円80銭)の切手を貼ってある。それをフロントのマネージャーに渡すと、2角(32銭)不足だというのである。
実のところ私も日本から中国へ出す国際便(封書)は90円と言うことは知っていても、[はがき]が幾らなのかは知らない。
黄龍のような山奥から手紙を出す場合、切手は売っていないから、手数料込みで1枚につき5元払って出して貰うのである。ですがその場合、請け負った人が現金だけ自分のものにしてしまい、絵はがきは捨てられちゃう? 危険があるので、何回も残念な思いをしてるから、何とか自分で切手を買うようにしてきたのである。
これでも4角多いのだから大丈夫だと説明しても、なかなか受けとってくれない。ボーイの一人に国際郵便はがき料金は4元2角ですよね? と相槌を促すと、これでOKだとホローしてくれたので、一件落着となった次第である。
黄龍から出した絵はがきは、私が7月6日にタイ旅行のバンコクから出した絵はがきの後、7月の20日頃着いたと友人から電話があった。投函してくれたのだなと、ほっとした。
目の中にあの光景を焼き付けて、高地トレッキングを堪能し、もう高山病の心配はなし、ビールを美味しく飲んで、昼食後は再び移動開始である。4,200mの峠を戻ります。午後2時過ぎには薄日も漏れて、峠の頂上付近の“白いシャクナゲ”が鮮やかに咲き競うのが楽しめた。満開を終え、茶っぽい感じにはなっていたが、どうしてこんな高地に群生しているのか不思議だった。
雑草の中に黄色い“罌粟”に混じって赤い“罌粟”もちらほら見える。7月になると、峠は“赤いシャクナゲ”でいっぱいになり、赤い“罌粟”が黄色に取って代わるそうである。
見晴台付近で“白いシャクナゲ”をバックに写真を撮った。
富士山より高い所に草木が群生しているなんて、どうしても今居る所が4,200mとは信じられなかった。
峠を逆戻りして、[川主寺]迄は42㎞。そこから一般道路に入り[九寨溝]までは46㎞。早い時間にホテルに入り、明日に備えるというスケジュールである。
[川主寺]からの川沿いの景色は、何処を向いてもキャベツ畑ばっかりだった。一年中キャベツが育つので、作りすぎで運搬費用にもならない安値になった時もあったとか?
夕方5時半過ぎに[九寨溝風景区]ゲートをくぐった。
一瞬私は自分の名前が変わって、浦島太郎になってしまったのかと思ってしまった。1998年10月に来た時と、街の風景がすっかり様変わりしていたのである。
あのときはホテルと言っても民宿程度のこぢんまりした建て物ばかりだった。素晴らしい紅葉の季節でも10月に入ればシーズンオフだからと、殆どのホテルが閉めていたので、宿を探すのに随分苦労させられた。
四川省と言えば中国大陸のド真ん中だから、10月と言えどもさぞかし気温が高いものと勝手に憶測して、厳冬用の備えなんかしてこなかった。ところが標高3,000mともなると、其処はすでに真冬の状態だった。寒かったら服を買えばいいやと安易に考えていたが、山岳地帯に洋服なんか売っている所はない。
着替えに持参した衣類という衣類を全部重ね着をしても、寒いのである。暑いのは我慢できても、寒いのは辛いもので、恥ずかしくも歯の根が合わない。かき氷を食べた時のような悪寒が頭の芯までツーンとくるのである。勉強不足だった。(苦い体験をしていたから、今回は革製のジャンぱーなんかも持参している)
ホテルに入れば少しは暖を取れるだろうと、何とか潜り込んだホテルには暖房装置などありませんでした。
マネージャーを呼んで暖房のある部屋はないのかと聞きますと、
「ここは夏だけの観光地で、最初っから暖房なんかありません。それにもうシーズンオフなので、店仕舞いをしようと思っていた所です」とまあこんな答えが返ってきたものである。
仕方がないから他の部屋からも掛け布団を運ばせて、蓑虫みたいにくるまって暖を取り、寒さを凌いだのを今でも忘れることが出来ない。
一般道路の左側は斜面状になってい、右側には川が流れている。その川向こうに、立派な建物が並立していた。あれらがみんなホテルなのだと説明されて吃驚した。
河原の広いスペースをふんだんに使って、横に広々と作ってある。
背の高いホテルでも4階建てぐらいで、それぞれが工夫を凝らした作りになっていた。少数民族の特徴をあしらった、建築美? それに方形や円形の劇場らしき物が必ずくっついていて、それが良く目立つ。
こんなに沢山建てちゃって、これだけの収容施設を埋めるだけの観光客が果たしてやって来るのだろうか? よけいな心配をしてしまう。
ガイドの王さんの説明では、台湾・香港の華僑が出資しているのだそうで、将来を見越しての投資だとか?
「土地は有り余る程有りますから建物も大きく広くなります」ですって。
4年前の[九寨溝]は未だそんなに知られていなかった。10月の紅葉季、一番美しい[九寨溝]を観光に来る日本人なんて殆ど居なかったし、中国人の観光客もまばらだった。
こんな広大な大自然の中に、ぽつりといる自分が九寨溝を独り占めしちゃったような、ぞくぞくする満足感を味わったものだった。
